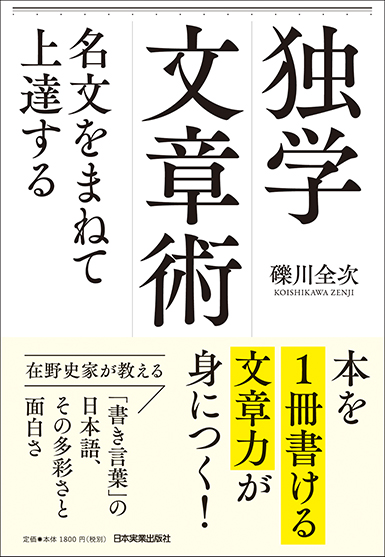在野の歴史研究家として、『独学で歴史家になる方法』(小社刊)など多くの著書を持つ礫川全次(こいしかわぜんじ)氏。最新刊『独学文章術』では、「文章上達の極意は名文をまねること」というスタンスから、明治の近代口語文草創期の福沢諭吉、夏目漱石や現代を代表する書き手、村上春樹までのそうそうたる歴史的名文家に加え、父の復員を待ちわびる終戦直後の小学生の手紙、話し家の話芸の文章化や映画監督のエッセイなどにいたる多彩な「名文・迷文」を取り上げ、その文体の核をなす論理や息づかいを読み解きます。
本書は全28講からなり、各講で名文を取り上げて解説、さらに演習と設問によって理解を深める、という構成です。その中から2講を選び、公開します。
ひとつめは第6講、テーマは「明確なメッセージを発しよう」です。紹介されている映画監督伊丹万作のメッセージは、時代を超え、コロナ禍に直面する現代の私たちの社会、世間にも向けられているように感じられます。
※数字表記など一部再編集しています。
『独学文章術 名文をまねて上達する』(礫川全次・著)より
第6講 明確なメッセージを発しよう
映画監督として知られた伊丹万作(いたみまんさく、1900~1946)に「戦争責任者の問題」というエッセイがあります。次に、その一部を引いてみます。初出は、『映画春秋』の創刊号(1946年8月)ですが、「青空文庫」から引用します。かなづかいは青空文庫のままです。
さて、多くの人が、今度の戦争でだまされていたという。みながみな口を揃えてだまされていたという。私の知つている範囲ではおれがだましたのだといつた人間はまだ一人もいない。ここらあたりから、もうぼつぼつわからなくなつてくる。多くの人はだましたものとだまされたものとの区別は、はつきりしていると思つているようであるが、それが実は錯覚らしいのである。たとえば、民間のものは軍や官にだまされたと思つているが、軍や官の中へはいればみな上のほうをさして、上からだまされたというだろう。上のほうへ行けば、さらにもつと上のほうからだまされたというにきまつている。すると、最後にはたつた一人か二人の人間が残る勘定になるが、いくら何でも、わずか一人や二人の智慧で一億の人間がだませるわけのものではない。
すなわち、だましていた人間の数は、一般に考えられているよりもはるかに多かつたにちがいないのである。しかもそれは、「だまし」の専門家と「だまされ」の専門家とに画然と分れていたわけではなく、いま、一人の人間がだれかにだまされると、次の瞬間には、もうその男が別のだれかをつかまえてだますというようなことを際限なくくりかえしていたので、つまり日本人全体が夢中になつて互にだましたりだまされたりしていたのだろうと思う。
このことは、戦争中の末端行政の現われ方や、新聞報道の愚劣さや、ラジオのばかばかしさや、さては、町会、隣組、警防団、婦人会といつたような民間の組織がいかに熱心にかつ自発的にだます側に協力していたかを思い出してみれば直(す)ぐにわかることである。たとえば、最も手近な服装の問題にしても、ゲートルを巻かなければ門から一歩も出られないようなこつけいなことにしてしまつたのは、政府でも官庁でもなく、むしろ国民自身だつたのである。私のような病人は、ついに一度もあの醜い戦闘帽というものを持たずにすんだが、たまに外出するとき、普通のあり合わせの帽子をかぶつて出ると、たちまち国賊を見つけたような憎悪の眼を光らせたのは、だれでもない、親愛なる同胞諸君であつたことを私は忘れない。もともと、服装は、実用的要求に幾分かの美的要求が結合したものであつて、思想的表現ではないのである。しかるに我が同胞諸君は、服装をもつて唯一の思想的表現なりと勘違いしたか、そうでなかつたら思想をカムフラージュする最も簡易な隠れ蓑としてそれを愛用したのであろう。そしてたまたま服装をその本来の意味に扱つている人間を見ると、彼らは眉を逆立てて憤慨するか、ないしは、眉を逆立てる演技をして見せることによつて、自分の立場の保鞏(ほきょう)につとめていたのであろう。
少なくとも戦争の期間をつうじて、だれが一番直接に、そして連続的に我々を圧迫しつづけたか、苦しめつづけたかということを考えるとき、だれの記憶にも直ぐ蘇よみがえつてくるのは、直ぐ近所の小商人(こあきんど)の顔であり、隣組長や町会長の顔であり、あるいは郊外の百姓の顔であり、あるいは区役所や郵便局や交通機関や配給機関などの小役人(こやくにん)や雇員(こいん)や労働者であり、あるいは学校の先生であり、といつたように、我々が日常的な生活を営むうえにおいていやでも接触しなければならない、あらゆる身近な人々であつたということはいつたい何を意味するのであろうか。
被害者を装ってはいけない
「だまされていた」と、被害者を装うことによって、「戦争責任」を他人に押しつけることは許されない。──これが、このエッセイで、伊丹万作が強調したかったことです。文章はわかりやすく、論理的です。「例」の引き方も巧みです。
当時、「被害者」を装っていた多くの日本人に対して、あるいは、このエッセイを読んでいる読者諸氏に対して、伊丹は、強烈なメッセージを放っています。
政治学者の丸山眞男は、1946年(昭和21)3月に、「超国家主義の論理と心理」という論文を発表しました。この論文の趣旨は、伊丹のエッセイと通じるところがあります。つまり、伊丹の主張するところは、完全なオリジナルとは言えない可能性があります。
しかし、わかりやすさ、説得力という点で、何よりもメッセージ性という点で、伊丹のエッセイは、丸山の論文よりも勝っています。
ここで、メッセージ性のある文章が成り立つ条件を考えてみましょう。まず、その書き手の側が、明確なメッセージを持っていなければなりません。また、そのメッセージを読み手に伝えたいという意思がなければなりません。その上で、書き手には、明快な論理、適切な例示、わかりやすい文体を駆使できる力量が求められます。
一方、そのメッセージが受け入れられるためには、それが月並みでなく、新鮮なものである必要があります。「月並みでない」と言っても、常識とかけはなれたものでは、世間に受け入れられません。世間の人々がウスウス気づいていながら、まだハッキリした形では言語化されていなかったようなもの、それが、「新鮮な」メッセージです。
伊丹万作のエッセイ「戦争責任者の問題」には、明確にして新鮮なメッセージが盛りこまれています。そのメッセージは、多くの日本人がウスウス気づいていたことであり、多くの日本人の痛いところを突いています。そのメッセージが盛られた文章は、論理的で、わかりやすく、説得力があります。ここでは、最初のほうの一部しか紹介できませんでしたが、読者の皆さんには、ぜひ、全文を読まれることを、お勧めします。
と申し上げたところで、設問です。
伊丹万作は、このエッセイで、右に引用した部分のあとも、いろいろなことを述べています。以下に、そうした言葉を引いてみますが、このなかに、ひとつだけ、伊丹が「言っていない」言葉がまざっています。その言っていない言葉を指摘してください。
設問6
1 私はさらに進んで、「だまされるということ自体がすでに一つの悪である」ことを主張したいのである。
2 だまされるということはもちろん知識の不足からもくるが、半分は信念すなわち意志の薄弱からくるのである。
3 家畜的な盲従に自己の一切をゆだねるようになってしまっていた国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任などが悪の本体なのである。
4 「だまされていた」といって平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でもだまされるだろう。
5 一度だまされたら、二度とだまされまいとする真剣な自己反省と努力がなければ人間が進歩するわけはない。
6 私は本質的には熱心なる平和主義者である。
7 戦争が始まってからのちの私は、ただ自国の勝つこと以外は何も望まなかった。
8 一本の戦争映画も作らなかったという理由から、私には人を裁く側にまわる権利がある。
解答
8
解説
1から7までは、すべて、「戦争責任者の問題」にある伊丹自身の言葉です。8だけは違います。伊丹は、戦争中、「自国の勝つこと以外は何も望まなかった」自分が、「偶然のなりゆきから一本の戦争映画も作らなかったというだけの理由で、どうして人を裁く側にまわる権利があろう。」と述べています。
伊丹万作は、このエッセイの最後に、自分は、「ほとんど日夜静臥中の病人」であると述べています。このエッセイも、病床で書いたのでしょう。伊丹は、寝たままで字を書く場合、文字はカタカナのほうが書きやすいと言っていました(「カタカナニツイテ」、大江健三郎編『伊丹万作エッセイ集』筑摩書房、1971)。この文章も、原稿段階では、カタカナ文だった可能性が高いと思います。なお、伊丹は、このエッセイが発表された直後の9月21日に、46歳で亡くなっています。
■第6講 まとめ
▼文章を書く以上、書き手は、文章に明確なメッセージを盛る必要がある。
▼文章の書き手は、読み手にメッセージを届ける意思がなければならない。
▼文章の書き手には、明快な論理と平明な文体を駆使する力が求められる。
著者プロフィール
礫川全次(こいしかわ ぜんじ)
1949年生まれ。1972年東京教育大学卒業。在野史家。「歴史民俗学研究会」代表。フィールドは近現代史、犯罪民俗学、宗教社会学。著書:『独学で歴史家になる方法』(小社)、『史疑 幻の家康論』『戦後ニッポン犯罪史』『大津事件と明治天皇』『サンカ学入門』『攘夷と憂国』『独学の冒険』『雑学の冒険』(以上、批評社)、『サンカと三角寛』『知られざる福沢諭吉』『アウトローの近代史』『日本人はいつから働きすぎになったのか』『日本人は本当に無宗教なのか』(以上、平凡社新書)他多数。