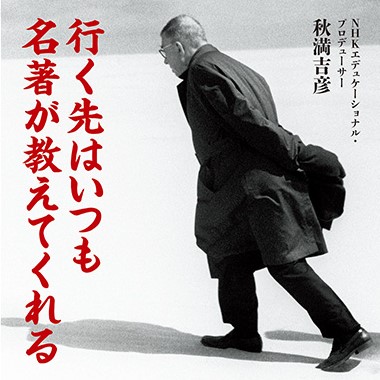砂丘を力強く歩くサルトルの写真を使った表紙が印象的な『行く先はいつも名著が教えてくれる』は、NHKの人気番組「100分de名著」のプロデューサーを務める秋満吉彦氏が、自身の人生に強い影響を与えた「名著」との出会いを綴った本です。名著のエッセンスを知ることができるブックガイドであり、また、一人のビジネスマンの内面の変化を通して読書という行為の意味を考えるきっかけになる本でもあります。
ここでは、本書で取り上げられている12の作品から2つをピックアップし、著者の「名著体験」がどのようなものだったのか、要約して紹介します。
人生から求められているもの──フランクル『夜と霧』
決して忘れることのできないフレーズ
ヴィクトール・フランクル『夜と霧』と著者との出会いは、哲学を勉強していた大学院時代。「哲学の研究者」になりたいという夢を持ちながらその狭き門に立ち向かう覚悟も自信もなく、就職活動への意欲もわかないまま焦りだけが募っているときでした。
著者の苛立ちを感じ取った後輩からすすめられた『夜と霧』は、ナチスによるユダヤ人強制収容所での出来事のドキュメントとそれに対する思索を記述したものです。そこで語られるエピソードには、極限状態にあっても輝きを失わない人間の尊厳、苦しみの底にあってもなお朽ちない人間の希望が、力強く表現されていました。当時落ち込んでいた著者にとっては気付け薬のように効いたそうです。
そして、「決して忘れることのできない」次のフレーズに出会います。
(『行く先はいつも名著が教えてくれる』14ページより)
このフレーズによって、「世界がぐるんと裏返った」と著者はいいます。
これまでの自分は人生に何かを求めていただけだった。だが、大切なのは、人生が私に何を求めているかなのだ。人生が私に何かを求める? その何かってなんだ? どうやったらそれを知ることができるのだろう。
それからというもの、「何になりたいか」ではなくて、「自分に何が求められているのか」ということを基準に物事を考えるようにしました。簡単にいえば、自分の欲望ではなくて、自分の信頼する先輩や教師に、自分を客観的に見てもらい、自分が求められている能力や、どんなことに役立つ才能をもっているかということを助言してもらうのです。
(14ページ)
『夜と霧』に出会ったことで、他者の視点も助けに自分を客観的に見つめ直した著者は、やがて「人の話を取材してまとめ、伝えていく仕事」に就く「夢」を持つようになります。それは単なる自分の欲望ではなく、人生に求められていることを考え抜くことによって立ち上がってきたものであるがゆえに、おのずとかなう「夢」でした。
自分に届く声をつかむ
『夜と霧』で描写される地獄のような極限状況や、そこにあっても決して尊厳を失わない人間という存在の力強さから、読者は様々なことを感じ、“体験”するでしょう。著者は、「人生は私に何を求めているのか」という言葉をこの名著から聞き取りました。こうした“体験”は、読者が置かれた状況によってまったく違ったものになるでしょう。
読み方に、正解や完璧な答えがあるわけではありません。作者の意図を越えたところで、自分に届いてくる「声」をつかむこと。これこそが真の読書体験なのではないかと、最近、身に染みてわかってきました。そうやって出会った言葉は、知的に理解しようとしたり、情報として記憶しようとしたりした言葉とはまったく違って、文字通り、自分の血肉になっていると実感します。
(17ページ)
自分をからっぽにする──岡倉天心『茶の本』
思い通りにいかない組織
NHKのプロデューサーという立場は「花形の職業」のように見えます。しかし実態は一般のビジネスパーソンとあまり変わらず、地方への転勤や希望とはまったく違う部署への異動もよくあること。希望通りの仕事をしている人はごく少数だそうです。
他方で番組に対する責任は非常に重く、著者は何度もストレスから逃げ出したくなったとか。とりわけ40代の中間管理職時代に直面した、番組制作チーム内の感情的な対立は、一時コントロール不能な状況にまで陥ったピンチでした。
当時著者が所属していたのは、NHKの職員と外部の制作プロダクションの混成チームでしたが、その両者の間には、仕事のしかたや意識の違いから軋轢が生じていました。両者からの相談や意見、愚痴までもがすべて著者のもとに押し寄せ、しかも上司は、非常に優秀な人物だったのですが、畑違いのジャンルだったために慣れない仕事を著者に振りがち。やりたい仕事がスムーズに進まず、ストレスは頂点に達していました。
そんなときに読み始めたのが、以前から関心があった、日本近代美術の立役者である岡倉天心の『茶の本』でした。「いまの現場から逃げ出すためには新規の企画を通すしかない」と考え、企画の参考にしようと手に取ったものでしたが、次の一節は想像していなかった影響を著者に与えました。
(『行く先はいつも名著が教えてくれる』38ページより)
自分の利害や求めることから離れる
「自分をからっぽにして自由に他人が出入りできるようにする」。すぐにはピンときませんが、天心の生涯を知ると理解できる、と著者はいいます。
天心は明治時代の文部官僚として、東京美術学校(現・東京藝術大学)の立ち上げなどに尽力しましたが、その強すぎるリーダーシップが反感を買い学校を追われるという挫折を味わいます。隠遁生活に入ってもおかしくない状況のなか天心はアメリカに渡り、ボストン美術館に職を得ます。日本文化の精髄を世界に知らしめようと『茶の本』を英語で執筆したのはその頃でした。
立場や考えに固執せず、自分にとって厳しい状況や環境、異なる文化や他者を丸ごと受け容れることで、やがて状況そのものを味方にすることができる。天心の「からっぽの思想」は彼の体験から生まれたものだと、著者は解釈しました。
天心の思想に触れた著者は、自分の利害や「やりたいこと」からいったん離れて自分をからっぽにしてみようと決意し、メンバーからの意見や相談を一切の先入観なしに聞きます。
私は、今までストレスにしか思えなかったみんなからの相談を、意識を変えてじっくり聞いてみることにしました。すると、単なる愚痴にしか聞こえてこなかった話が、実はいろいろなヒントや意味をはらんだものだ、ということに気づけるようになりました。単なる愚痴として聞いてしまうと、ストレスにしかならないのですが、すべてが建設的なものを何がしか含んでいるととらえてみると、それがヒントの宝庫になっていきます。
(45ページ)
中間管理職である著者が触媒のように機能し始めたことでチーム内の風通しが見違えるように良くなり、それぞれが実力と個性を発揮し、ひいては大変大きなプロジェクトを成功させるまでになったそうです。
『茶の本』は日本文化の美意識と精神性を西洋人に伝えるために書かれたものですが、著者にとってその精神性は、困難な状況を自在にコントロールする心のありようとして理解されたのでした。
*****
以上2つのエピソードは、『夜と霧』や『茶の本』から秋満氏が受けた影響の一部にしかすぎません。本書には、12の名著との出会いによって動かされた著者の内面の変化が丁寧に綴られています。
名著体験は読み手の数だけあります。まだ体験していない名著があるなら、こんなに楽しみなことはありません。
『行く先はいつも名著が教えてくれる』で取り上げられている12の名著
- フランクル『夜と霧』
- 河合隼雄『ユング心理学と仏教』
- 岡倉天心『茶の本』
- 神谷美恵子『生きがいについて』
- レヴィ=ストロース『月の裏側』
- 宮沢賢治『なめとこ山の熊』
- ガンディー『獄中からの手紙』
- 『維摩経』
- 三木清『人生論ノート』
- ミヒャエル・エンデ『モモ』
- 『荘子』
- 『歎異抄』
(登場順)