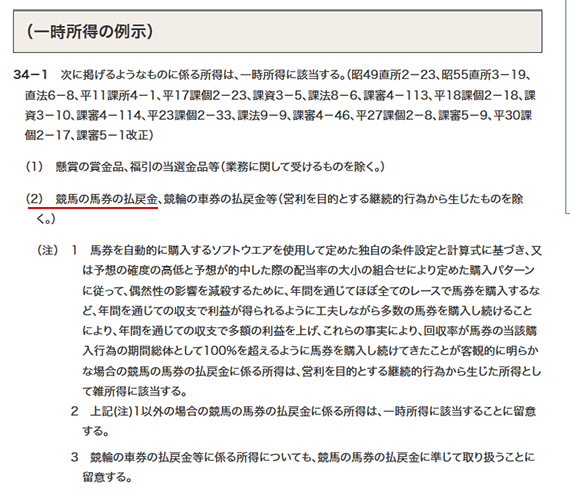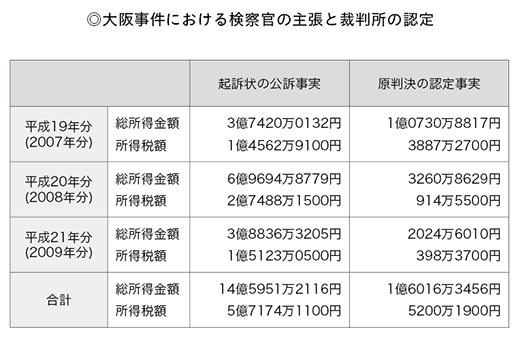消費税・相続税・固定資産税……etc. 日本に住んでいる以上、いろいろな名目で税金を納めなければなりません。その中でも最も身近なのが「所得税」でしょう。サラリーマンであれば基本的には天引きで、事業を営んでいる場合や極めて高収入のサラリーマンなどは確定申告を行うことで納めています。
所得税とは、文字通り“所得(ここではひとまず「収入から経費を差し引いたもの」と定義します)”にかかる税金ですが、この扱いに関して一部の注目を集めていた「ある裁判」が、2018年8月末に決着しました。
外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴(18/8/31、朝日新聞)
一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。
一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。(一部抜粋)
このように「競馬(正確には、そこから得られる払戻金)と税金」に関して争われた裁判はいくつかあります。たとえば2017年12月には、最高裁で以下のような判決がでています。
外れ馬券「経費」認める 最高裁判決(17/12/15、日経新聞)
競馬の馬券を継続的に大量購入していた北海道の男性が、所得税の申告で外れ馬券代を経費と認めるよう求めた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第2小法廷(菅野博之裁判長)は「外れ馬券代を経費に算入できる」と認め、国の課税処分を取り消した。男性の勝訴が確定した。
最高裁は2015年、外れ馬券を巡る所得税法違反事件の判決で、馬券を自動的に大量購入するソフトを使った例について「外れ馬券代は経費に当たる」と初判断した。
今回の男性はソフトを使わず、レースごとに競走馬のコース適性や枠順、騎手の技術などから着順を予想。配当金額と予想の確度を組み合わせる独自のノウハウで05~10年に約72億7千万円分の馬券を買い、約5億7千万円の利益を上げた。
第2小法廷は判決理由で「男性の馬券購入は営利目的の継続的な行為であり、利益を得るために不可欠な外れ馬券代は経費とするのが相当だ」と指摘。ソフトを用いない購入方法でも外れ馬券を経費と認めた。(一部抜粋)
前者(2018年8月の最高裁判断)は「競馬の払戻金を事業所得といえるのか、それとも一時所得になるのか」について、後者(2017年12月、および引用中にある2015年の最高裁判断)は「外れ馬券は経費として認められるのか(言い換えれば払戻金は雑所得か、それとも一時所得か)」について争われたものです。
そして前者については「払戻金は一時所得であり、事業所得としては認められない」、後者については「外れ馬券の購入費も経費としても認める(=雑所得である)」という判決が下されました。
それでは個々の判決と「競馬と税金」の関係について、所得税法の観点から時系列で見てみましょう
※本記事は『教養としての「所得税法」入門』木山泰嗣著(2018年8月発刊)の内容を基に作成されています。
払戻金は雑所得か、一時所得か(2015年・17年の最高裁判断より)
前述の通り、2015年および2017年の裁判では「外れ馬券は経費として認められるのか」が争点でした。報道や公開されている判決文に基づき、2015年の裁判についてかみ砕いて書くと以下のようになります。
- 大阪の会社員男性が、JRAのサービス経由で馬券を自動購入できるソフトを使用し、数年以上にわたって大量購入していた。その際、自分で「勝てる条件(組み合わせと購入額)」を分析・計算し、ソフトに入力していた。
- その買い方は、中央競馬で開催されるほぼすべてのレースを網羅し、一日当たり数百~数千万円、一年当たりにすると10億円前後に及んだ。こうした買い方は、勝ち負けの偶然性を限りなく抑え、長期的に見て「払戻金の合計額-外れを含む全馬券の購入代金の合計額」がプラスになるようにしたものだった
- この購入戦略は大当たり。2005~09年で総計35億1千万円分の馬券を買ったところ、払戻金を36億6千万円得た(計算上の利益は約1億5千万円)。後述の裁判で争われた2007~09年に限ってみても、約1億3900万円の利益を得ている。
- 国税庁は、こうして競馬で得た多額の利益を問題視。当時の法解釈に則って「経費として解釈できるのは当たり馬券の購入額だけ」と限定。男性を所得税法違反の被告人とし、2007~09年に男性が得た利益の約4倍に当たる「所得税約6億8千万円と無申告加算税1億3千万円」を課す内容の起訴をした。
- 一審、二審ともに男性の主張が認められた。そして2015年、最高裁は「外れ馬券代は経費に当たる」と判断し、一審、二審と同じ結論を下した。これに伴い「課税処分の取消し」を求めた民事裁判でも男性の主張が認められた。
ちなみに、2017年に確定したほうの裁判も同様の争点になっています(ただし、自動購入ソフトを使わずに購入していたという点において異なる)。
先にも触れた通り、これら一連の裁判の核は「外れ馬券を加えた全馬券の購入費も経費として算入できる(=雑所得となる)か、直接的に払戻金を得た当たり馬券だけが経費として認められる(=一時所得となる)か」ですが、その判断を下すにあたっては「これらの利益が一時的に得た(正確には、非継続要件を満たす)収入ではない」と認められるのかどうかがポイントとなりました。
2015年の最高裁判断はどのようなものであったのか

では、2015年の裁判について見てみましょう。木山氏は『教養としての「所得税法」入門』(以下、本書)で以下のように解説しています。
第1審から上告審まで一貫して争われたのは、外れ馬券の購入代金も所得金額を計算する際に控除できるか、でした。競馬の馬券の払戻金は、当時の通達によれば一時所得にあたると規定されていました(所得税基本通達34-1(2)、下図赤線部参照)。
(2018/9/18時点の「国税庁 法令解釈通達」のキャプチャを一部編集) なお、この「所得税基本通達34-1(2)」の記述に関して、後ろにかっこ書・注書が記載されています(2018年9月現在)が、これらは2015年および17年に出た、一連の最高裁判断後に付け足されたものです(詳細は後で解説します)。
さて、当時の通達に従って解釈した場合、これらの払戻金は一時所得にあたり、収入を得るために「直接に要した」支出金額だけが控除できることになります。そうすると、当たり馬券の購入代金は控除できますが、外れ馬券の購入代金は控除できないことになります。
一時所得であれば1/2課税だからよいではないかと思われるかもしれませんが、競馬事件では外れ馬券の購入代金を控除できるか、できないかで、所得金額、ひいては所得税額が大きく変わるため、この点が争われたのです。
3年間(2007年分から2009年分)で、被告人は28億6951万円の馬券を購入し、30億0979万円の払戻金を得たのですが、馬券購入代金のうち27億4008万円が外れ馬券の購入代金だったという事案だったからです。
大阪事件(注:2015年に最高裁判断が下された事件)における所得金額と所得税額の対比(一時所得と主張した検察官の起訴状記載の公訴事実と、雑所得と判断した裁判所の認定事実)をみると、下表の通りです。
(本書P.295より、一部編集のうえ引用) このように、裁判所は一貫して第1審から上告審まで被告人(弁護人)の主張を認め、一時所得ではなく雑所得であるとして(雑所得であれば間接対応を含めた必要経費を控除できます)、外れ馬券の購入代金の控除を認めました。
大阪事件の上告審判決(最高裁2015年判決)が、同種事件が複数ある競馬事件のなかで最初の最高裁の判断になりました。また、一般論としても、一時所得の非継続要件についての判断基準を示したものとして、先例になりました。判決は、次のようなものでした(青字部分が判決文、以下同様)。
「……所得税法上、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。」
ポイントは、「行為」だけでなく「利益」についてもみたうえで、継続性があるかないかをみるというものです。「利益」も考慮するのは、非継続要件は「営利を目的とする継続的行為」ではないことであり、「継続的行為」だけでなく「営利を目的とする……行為」の部分も判断しなければならないからです。
そのうえで、「被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいて、インターネットを介して長期間にわたり、多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより、多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえる」などの事実が認定された大阪事件の事案では、継続性がないとはいえない(非継続要件を満たさない)としました。
このように最高裁が考えたのは、一連の行為を全体的にとらえたためです。その結果、外れ馬券の購入代金も直接要したものとして必要経費として控除できるという判断となりました(直接対応なのか、間接対応なのかについて明示はしていませんが、前者であると認定しているように考えるのが自然でしょう)。
(本書P.294-297より、一部編集のうえ引用)
2015年5月、この判断を受け「所得税基本通達34-1(2)」には下記のかっこ書・注書が付け加えられました。
(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
- 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
- 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
(本書P.298より)
これを注意深く読むと、先ほどの図中にある文面とは微妙に異なることがわかります。では、次に2017年の最高裁判断を見てみましょう。
2017年の最高裁判断はどのようなものであったのか

こちらは、一審は国が、二審の高裁は男性がそれぞれ勝訴し、最高裁で高裁判断が支持されるという展開でした。
こちらは自動購入ソフトを使った購入ではなかったため、一審では基本通達に追加された“自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいて”という記述には当たらないこともあってか、「一般的な競馬ファンの購入方法と大きな差がない」と判断。国側の主張を認めたものの、二審では男性が逆転勝訴。最高裁も二審判決を支持し、外れ馬券の経費扱いが認められました。そのときの最高裁判断は以下のようなものでした。
被上告人(編集注:男性のこと)は、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って馬券を購入することとし、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら、6年間にわたり、1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けたというのである。
このような被上告人の馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様に照らせば、被上告人の上記の一連の行為は、継続的行為といえるものである。
そして、被上告人は、上記6年間のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上、その金額も、少ない年で約1800万円、多い年では約2億円に及んでいたというのであるから、上記のような馬券購入の態様に加え、このような利益発生の規模、期間その他の状況等に鑑みると、被上告人は回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえるのであって、そのような被上告人の上記の一連の行為は、客観的にみて営利を目的とするものであったということができる。
以上によれば、本件所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として、所得税法35条1項にいう雑所得に当たると解するのが相当である。
(最高裁判例引用)
判決文特有の文章ということもあり若干読みづらいですが、要するに「自動購入ソフトによらない購入であっても、6年間ほぼすべてのレースで偶然性を排除し、利益が得られるように工夫して得た利益である以上、継続的に得た所得(≒雑所得)と認定するのが妥当」ということになります。
これらの結果「所得税基本通達34-1(2)」は、先ほどの画像のような記載になったのです。そのうえで、木山氏は次の点を指摘しています。
租税法律主義の下で通達の規定は課税要件とならず、そもそも参考レベルに過ぎないものです。
しかし、2015年に最高裁判決が出たことで改正したにもかかわらず、その数年後に再び最高裁判決が出たことでさらに改正されました。国税当局としては、後手にまわる状況になってしまったことを否めないでしょう。
もっとも、この2つの最高裁判決をみても(また改正された通達の規定をみても)、実際に、どの程度の回数、金額の購入が何年程度続き、利益がどれくらい出ていれば、馬券の払戻金による所得が原則である一時所得ではなく、(非継続要件を満たさないとして)雑所得になるのか、その明瞭なメルクマール(編集注:指標)はないというほかありません。
(本書P.301-302より)
事業としての「馬券購入業」の成立の是非(2018年の最高裁判断より)
次に、所得税法の観点からみた「事業としての馬券購入」についてみてみましょう。本記事冒頭に上げた引用を改めて掲載しますが、
外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴(18/8/31、朝日新聞)
一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。
一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。(一部抜粋)
これによると、先ほどの「自動購入かどうかを問わず、馬券は経費として認められた」という判断とは異なる結果になっています。
この点について裁判所は、次のように「事業」といえるためには「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性」が必要であると判示しました(この可能性は「所得発生の安定性」と呼ばれているため、以下そのように表記します)。
そして、この納税者の5年分の競馬所得をみると、3年分について赤字が出ているため(2年分は黒字なのですが)、所得発生の安定性がないとして、事業所得にはあたらないとしました。
……事業所得にいう『事業』とは、対価を得て継続的に行う事業をいうものと解される。そして、事業所得にいう『事業』に当たるかどうかは、一応の基準として、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務に当たるかどうかによって判断するのが相当であり
(中略)
具体的には、営利性及び有償性の有無、反復継続性の有無に加え、自己の危険と計算においてする企画遂行性の有無、その者が費やした精神的及び肉体的労力の有無及び程度、人的及び物的設備の有無、その者の職業、経験及び社会的地位、収益の状況等の諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして、『事業』として認められるかどうかによって判断すべきものと解するのが相当である。
そして、社会的客観性をもって『事業』として認められるためには、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性がなければならないと解される。
(本書P.235-236より)
また、事業所得者の義務である「取引を記録した帳簿の作成・保存」を果たしていなかったことも裁判で指摘されています。このことからも、裁判所は「たとえ生計を成立させていたとしても、事業としては認められない」という結論に至ったと考えることができそうです。
こうした判断に対し、木山氏は「裁判所の判断の背後には『安易に事業所得と認めると、他の所得と損益通算することで節税できてしまうため認められない』というものがあったのかもしれない」と前置きをしたうえで、次のような見解を示しています。
- 5年のうち3年が赤字だったとはいえ、世間には赤字を出している会社は多数存在する。「事業」として認める要件にこうした所得発生の安定性を必須とするのは、事業所得の本来の姿とは異なる
- 所得税法施行令63条12項には「対価を得て継続的に行なう事業」としか書かれていない。有償で利益を得ればよく、それ以上に相手(この場合はJRA)に対して提供した役務の見返りであることまで必要ないのではないか
他方で一般論としては安易に「事業」を認めてしまうと、他の所得(給与所得)などがある者が損失の生じる事業を片手間に行い、それを「損益通算」するという節税のようなことが認められてしまう問題も生じます。裁判所の判断の背後には、このような考えがあったのかもしれません。
しかし、この事件の納税者は会社を退職しており、競馬のみで生計を立てていたのですから、事業所得を認めてもよかったのではないでしょうか。払戻金を支払うJRAに対しては役務提供をしていないかもしれませんが、大量に馬券を購入していますし、生計を立てるに足る収入が得られるように、さまざまな情報を得ながらノウハウを研究しているからです。
それが〇〇業という一般的に確立された事業ではないとしても、「対価(収入)」を得て継続的に行われているのであれば、それはその納税者にとっては「事業」であり、「事業から生じた所得」と考えられるはずです。
(本書P.239より)
以上、いくつかの「競馬の払戻金にまつわる裁判」を税法の観点から見てみました。こうした新しい稼ぎ方と税金に関して木山氏は、国税庁が公開しているタックスアンサーの内容を引用しながら、次のように述べています。
これらはあくまで一般論としての国税当局の見解に過ぎません。所得区分は、その所得を得た納税者の事例ごとに所得税法の規定の適用として判断することになります。いずれの例も、「事業性」があるとまではいえない程度の規模のものにとどまるという前提での解説(見解)と考えるのが自然でしょう。こうした話題の副収入について、裁判で争われる例が近い将来出てくる可能性は十分にあります。
(本書P.244より)
今回とりあげた競馬の例に限らず、「所得と税金」に対する考え方を身につけておくことは、「新しいお金の稼ぎ方」を考え出すうえでも有効なのではないでしょうか。