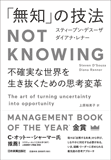リーマンショックの嵐が吹き荒れる2008年11月のこと。エリザベス女王は、ロンドン・スクール・オブ・ビジネスを訪問しました。高名な経済学者たちと面会した女王は、何気なく次のような質問をしました。
「信用収縮が進んでいたことに、なぜ誰も気づかなかったのですか?」
並み居る経済学者たちはこの質問に動揺し、その場では十分に答えられなかったため、後日要人を集めた大規模なフォーラムを開催して、女王への書簡をまとめました。公開されたその書簡には、多くの金融関係者が危機を予測し、数々の警告がなされていたことや、国際決済銀行が、金融市場にリスクが正しく反映されていない点について繰り返し懸念を表明していたことなどが記されていました。
つまり、金融市場に対する懸念は多くの人が持っていたのです。しかし──
「警告があったにもかかわらず、ほとんどの人は、銀行はみずからの行動をわきまえているものと確信していました。金融を操る魔術師が、リスクマネジメントの新しく賢い方法をひねり出しているのだろう、と信じていました。(……)当人たちも、みずからの判断に欠陥があるとか、自分が管理している組織のリスクを完璧に調べきれていないとか、信じたくはなかったのです」
書簡はこのように続き、そして、「かかわった個々人はきわめて知性が高い人々だったのに、傲慢さと、群集心理と、重要な役割を果たす専門家への盲信による集合的失態として、今回の金融危機は生じたのである」と結論付けています。
(以上、同書 CHAPTER1 46~48ページより)
金融危機に関してはまた、ノーベル経済学賞受賞者であるジョージ・アカロフが、2013年4月に行われた国際通貨基金(IMF)の会議において、経済危機を木に登った猫になぞらえてこう表現しています。
「猫を木から下ろす方法を考えなければならないが、誰もが猫を独自の視点で見て、独自のイメージをもっている。どの意見も同じではなく、どの見解にも根拠があるが、ひとつだけ確かなことは、何をなすべきか、我々はわかっていない、という点である」
心理学者ダニエル・カーネマンの指摘は、さらに踏み込んだものです。
「今になって大勢が、金融危機が訪れるのはわかっていた、と言う。それは真実ではない。危機後の我々は『理由はわかっている』と自分に言い聞かせながら、世界は理解可能なものだという幻想を守っているのだ。だがむしろ、世界はほぼ常に理解不可能なものだ、と認めるべきではないか」
世界はどんどん複雑化し、曖昧化しています。現代最高の知性を持つ専門家といえども、明確な将来ビジョンを描くことができない。それほど世界は、予見できない出来事に満ちているのです。
(以上、同書 CHAPTER3 81~83ページより)
「知らないこと」を恐れない
ムハマド・ユヌス。貧困層を対象にした無担保・低金利の少額融資を専門にするグラミン銀行の設立者であり、ノーベル平和賞の受賞者です。
ユヌスは、自分がもし銀行業務について何か知っていたら、そもそも低金利融資というプロジェクトに乗り出さなかっただろう、と話しています。
「知らないという前提で臨むことが、むしろメリットとなるときもあるのです。オープンになります。規則や手続きを心配せずに取り組むことができます。(……)私は、何も知らなかったからこそ挑戦できたのです」
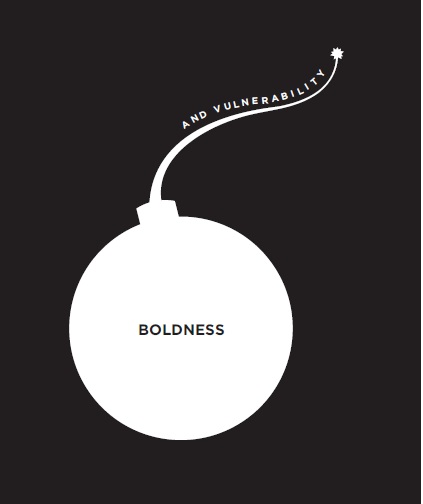
ユヌスは「知らない」という姿勢で課題に対峙し、プロジェクトをやり遂げました。もちろん、「知っている」こと自体が悪いわけではありません。しかし、ある事象について「知っている」という姿勢で臨むことは、時として、その事象に対する新鮮な視点をふさぐ壁になってしまうのです。
ユヌスは、若き起業家に対してこんなアドバイスを送っています。