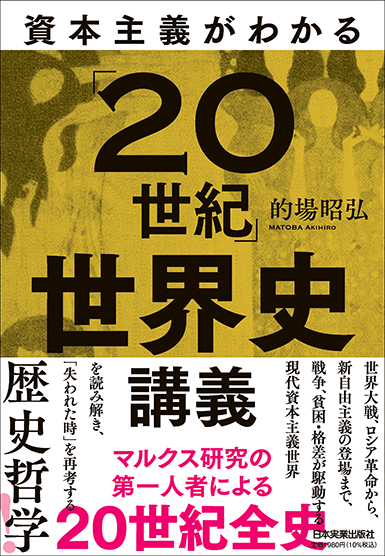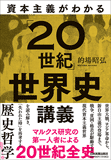世界大戦と革命の世紀にして西欧資本主義が頂点を極めた時代、「20世紀」の本質とは? ウクライナ戦争や中東有事の根源はどこにあるのか? マルクス研究の第一人者・的場昭弘が縦横に語る『資本主義がわかる「20世紀」世界史講義』。神奈川大学の大人気市民講座の内容をまとめた本書の「はじめに」の後編を公開します(前編はこちら)。
西欧化と自国主義とのジレンマ
18世紀は、こうしたヨーロッパで生まれたさまざまな成果が一挙にアジア・アフリカに流れ込んだ時代でした。それは「世界史」という概念が大きく変わった時代でもあったのです。
それまでの世界史はアジアがリーダーだったとはいえ、各地域がそれぞれ独自の歴史を刻んでいたのですが、18世紀からの世界史は、ヨーロッパが範を垂れて、ほかがそれに従うものになりました。国には序列が生まれ、国民にもその序列が浸透します。よりよく西欧化に適応できた国民が序列の上位にランク付けられることになるのです。ここからアジアの長い停滞が始まります。
ヴィクトリア時代のイギリスは、拡張するヨーロッパの象徴です。繁栄を極めるイギリスは大英帝国として“日が沈まない国”なのです。ヴィクトリア女王(1819〜1901、在位1837〜1901)は、英国ばかりか世界に広がった英国圏の女王でもあります。国民国家は、自国が安定すると、海外に進出することで帝国化するようになります。
帝国とはいえ、大英帝国はそれまでの大陸型の統一の緩い帝国とは異なります。英語という言語を話し、宗教は国教会を中心とするイギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド)が中核となり、その周辺に彼らが移住した地域、すなわちカナダ・アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド・南アフリカが連なり、その下に従属国があるという構図です。19世紀に生まれた人種論そのままに、アングロサクソンを頂点に、ラテン人、スラブ人、黄色人種、黒人といったランキングが存在しました。
その枠組みは今も相変わらず残っていて、たとえばコロナ禍において、アメリカで「#Black Lives Matter」運動が起きたのは、同じ災厄でも黒人などの貧困層に負担が重くのしかかったからです。ヨーロッパでいえば、移民・難民にしわ寄せがいきました。「白人の責務」(white’s burden)という言葉がありますが、それは白人が未開の文化を啓蒙し、発展させる義務を負っているということです。
それを言い換えると、「帝国の意識」ということになりますが、これはイギリスだけでなくフランス、ドイツにもありました。帝国の中心にいる宗主国の人種は、その帝国内の遅れた人種を啓蒙しなくてはなりません(ここで断らなければならないのは、「人種」という概念も、「民族」という概念も、19世紀に発見されたということです)。
こうした啓蒙思想は、実はルネサンス以降の西欧思想が行き着いた当然の結果でもあったのです。人々が経済的な豊かさを求めるという考えは、なるほど素晴らしいことですが、それが合理性や理性的なものを追求し、絶対的な真理を標榜するものになってくると、たちまち、ほかの地域よりも自らが秀でているという感覚が生まれます。19世紀に生まれたさまざまな西欧の学問は、一見きわめて実用的でありながら、実はヒエラルキーに基礎を置き、接する者に抑圧的に作用するものでした。
西欧の学問を手に入れることは、真理を学ぶことである以上に、西欧のこうした思想に屈服することでもありました。一気に西欧化を進めた日本のような国では、この問題が典型的に現れます。
しかし、その前例はロシアにあったのです。
ロシアは日本より200年前、ピョートル大帝(1672〜1725)の時代にギリシア正教会のビザンチン文化を棄て、西欧化の道を選びました。大帝は帝都サンクト・ペテルブルクを欧州の都市のようにつくり上げましたが、その後のロシアは、西洋化と自国主義の矛盾のなかにはまり込みます(今も抜け出せていません)。西欧化すればするほど、西欧からは見下される。その鬱積や怒りを非西欧にぶつけるという構図です。
明治維新以後の日本もまた、同じような轍を踏みます。西洋化にいそしむほどに“猿マネ”と言われ、学べば学ぶほどアイデンティティが失われていく。極東にあって、しかも西洋人とは似ても似つかない姿かたちをしている日本人の疎外感は、ロシア以上に大きかったかもしれません。西欧風の容貌や西欧語、西欧芸術や料理への憧れは、近隣アジアへの蔑視を生み出し、自らの文化の祖先(中国や朝鮮)を恨むことになるという問題です。
それと比べて、多くのアジアの国々、とりわけかつて文明の中心にいた中東・インド・中国は断固としてこの近代化を拒否します(トルコは19世紀前半に西欧化しますが、今もその揺り戻しのなかにいます)。そのために西欧との衝突に発展し、植民地になり、戦争に巻き込まれていきます。
しかし、この苦難の戦いは、自らの伝統を維持したがゆえに起きたことで、その後の近代化を自らのものにできたのも、それがあったからとも言えます。
ロシアと日本は、あまりにも安易、あまりにも軽率に西欧を受け容れたために、一時的には成功するのですが、長い目で見れば失敗している事例ということになります。
欧州第一主義に陰り
世界史という概念は、ヨーロッパの優位性を根底に置いています。一般的な世界史の教科書は、ヨーロッパ文明が優れているという前提で始まり、その起源をギリシア・ローマに求めます。停滞していた中世でさえも、ルネサンスをもたらした自己陶冶(とうや)の過程として描き出し、近代化、資本主義、民主主義、国民国家などはすべて西欧製で、それらを劣った国々に普及させることが西欧人の役割、白人の責務であるというストーリーを創作します。
西欧が生み出した文化・文明(宗教・教育・言語・建築など)は、資本主義という媒体を通して世界中に拡がります。これがまさにグローバル化の過程であって、グローバル化とはすなわち、世界のヨーロッパ化のことです。世界中に設けられた西欧語の学校・大学はその先鋒であり、キリスト教会は世界宗教キリスト教の販売促進部隊として活動していきます。その結果、豊かなヨーロッパ人は“最高人種”であるとして君臨することになりました。
19世紀の西欧の思想家や歴史家で、アジアやアフリカの側に立って世界を見ようとした者は、きわめて少数です。これはカント、ヘーゲル、マルクスなども例外ではありません。
アダム・スミスやリカードなどの自由主義経済を推進しようとする書物も、植民地になったアジアやアフリカの人々にとっては、有害図書の部類でしょう。資本蓄積のためには、対外進出が不可避であることを説いた書物だったからです。アジア侵略のヒントを与えられたと受け取った日本人にとっては、きわめて優れた書物だったということになりましたが。
1970年代の後半から、そもそもオリエンタリズム自体が西欧の視点によるものだという考え方が出てきました(サイード『オリエンタリズム』上下巻、今沢紀子訳、平凡社ライブラリー、1993年)。その提唱者であるエドワード・サイード(1935〜2003)はパレスチナ出身の学者でした。それゆえにこそ、こうした視点を持ち得たのだろうと思いますが、アメリカの有名なコロンビア大学の教授であったことも影響力を発揮できた一因だったというのは皮肉なことです。
他方、植民地支配や帝国主義を批判的にとらえるポストコロニアル理論に影響を与えたスチュアート・ホール(1932〜2014)はジャマイカ出身のイギリス人で、バーミンガム大学で勤務していましたが、彼は同大学の教授ではなく市民大学の一講師でした。その経歴が、ポストコロニアルの運動が一過性に終わる原因であったとも言えます。
2020年5月25日、黒人青年が白人警察官5人に殺害された事件を受けて、全米各地でデモが起き、それ以前から批判があったマーガレット・ミッチェル(1900〜49)の南北戦争を扱った長篇小説『風と共に去りぬ』が黒人差別を助長する作風だというので、その映画化作品の配信が一時、停止されました。たくましく生きる主人公の白人女性に感情移入できれば感動的な大作ということになるのですが、主人公に仕えるメイドや農園労働者などの黒人に感情移入すれば、これはとんでもない映画ということになります。
ことほどさように、我々は無意識のレベルで西欧の価値観に染め上げられています。
しかし、さしもの西欧第一主義も1918年(第一次大戦終結)以降、一変します。いよいよ西欧の自信に陰りが生じてきました。
その背景として、ヨーロッパでの悲惨な戦争があります。第一次大戦の戦死者は1600万人に達し、それまでの100年間の戦死者数を超えています。
ヨーロッパ中心の世界観を覆したものに、ベストセラーとなったオズヴァルト・シュペングラー(1880〜1936)の『西洋の没落』(第1巻・1918年。文献の直後に置かれた年数は原典の発行年とする。必要に応じて記載する。以下、同じ)があります。これはヨーロッパの歴史家による自作自演とも言うべく、差別するだけ差別し、ある時から改悛して平等主義者になるというのは虫が良すぎるのですが、影響力はその時代を支配する者にあるとするのなら、それしかないとも言えます。
ポストモダン、ポストコロニアルなどの西欧近代を否定する新しい思想が、シュペングラー以降、続々とアメリカやヨーロッパの白人社会で生まれるというのも、まさにその皮肉のひとつです。ジェンダーにしても同じです。西欧の帝国意識を批判する書物が、今日も西欧言語で出版され続けています。さらにそれを読む日本の学者たちは、近隣アジアの言語は知らなくとも英語やフランス語はできる。まさに皮肉な話です。私自身、そのピエロの一人ですが。
的場昭弘(まとば あきひろ)
日本を代表するマルクス研究者、哲学者。マルクス学、社会思想史専攻。1952年、宮崎県生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士。元・神奈川大学経済学部教授(2023年定年退職)。同大で副学長、国際センター所長、図書館長などを歴任。
著書に『超訳「資本論」』全3巻(祥伝社新書)、『未来のプルードン』(亜紀書房)、『カール・マルクス入門』(作品社)、『「19世紀」でわかる世界史講義』『最強の思考法「抽象化する力」の講義』(以上、日本実業出版社)、『20歳の自分に教えたい資本論』『資本主義全史』(以上、SB新書)、『一週間de資本論』(NHK出版)、『マルクスだったらこう考える』『ネオ共産主義論』(以上、光文社新書)、『マルクスを再読する』(角川ソフィア文庫)、『いまこそ「社会主義」』(池上彰氏との共著・朝日新書)、『復権するマルクス』(佐藤優氏との共著・角川新書)、訳書にカール・マルクス『新訳共産党宣言』『新訳初期マルクス』『新訳哲学の貧困』(以上、作品社)、シャック・アタリ『世界精神マルクス』(藤原書店)など多数。