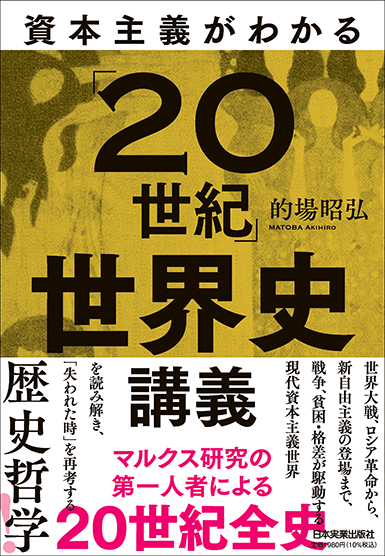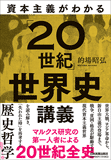世界大戦と革命の世紀にして西欧資本主義が頂点を極めた時代、「20世紀」の本質とは? ウクライナ戦争や中東有事の根源はどこにあるのか? マルクス研究の第一人者・的場昭弘が縦横に語る『資本主義がわかる「20世紀」世界史講義』。神奈川大学の大人気市民講座の内容をまとめた本書の「はじめに」を公開します。まずは前編から。
ヨーロッパの国民国家
本書の前史となる歴史的な事象について簡単に記していきましょう。本書は、『「19世紀」でわかる世界史講義』(日本実業出版社)の続編です。そこでは、「世界史」というものの背景を説明していますが、ここでもう一度簡単にその内容を述べてみます。

同書の対象となるのは13世紀から19世紀までで、そこで問題とされたのは、「世界史とは何か」ということでした。世界史とはモンゴルの東欧への進出によって生まれたのですが、その世界史の中心が、アジアから次第にヨーロッパへ変わっていき、最終的にヨーロッパを中心とする世界史という概念ができたのです。
このような新しい時代が開かれていく原因となったのが、国家の宗教からの独立であり、それはヨーロッパ内での国家間の抗争と競争力の増大をもたらしました。こうした国民国家の出現を促したものが、宗教改革です。宗教改革によって、単一のヨーロッパ帝国、すなわち神聖ローマ帝国が崩壊し、イギリスやフランスといった国民国家が成立します。モンゴルの侵入、ペストの流行によって激変したヨーロッパは、アジアのなかに強引に引き込まれ、変化を余儀なくされたのですが、そこから新たな国民国家という小国家が並び立つヨーロッパが生まれたのです。
小国の並立は小国同士の抗争(三十年戦争、七年戦争、ナポレオン戦争)の原因となり、結局、19世紀に見られる国民国家(Nation State)を生み出します。小国分離の状態は競争を惹起し、それが大航海時代になると、各国の海外進出競争を生み出し、アジアへの進出、やがてはその支配へと至ります。そして新大陸への進出により、北米・南米で略奪の限りを尽くし、植民地化していきます。
知的文化の発展
こうした政治・宗教・経済の動きには、文化的な動きも呼応します。たとえばルネサンス運動(14〜16世紀)においては、西アジアで発展した科学技術や古代ギリシア・ローマ思想(プラトン、アリストテレスなど)を受容し、新しい思想や文化を生み出します。マキアベリ(1469〜1527)からデカルト(1596〜1650)、カント(1724〜1804)、ヘーゲル(1770〜1831)に至る西欧思想の流れを見ると、ギリシア哲学の伝統を引き継いだ、宗教から分離した純粋哲学(知の探求学)の系譜があることがわかります。神を用いず自律的に思考しようとする姿勢は、社会科学や自然科学にも影響を与えていきます。
社会科学の世界、すなわち現実の政治・経済とのつながりのある実学の世界では、国民国家、聖俗分離、人民主権、民主主義、共和主義などがテーマとして取り上げられるようになります。
国民国家の成立期にホッブズ(1588〜1679)、ロック(1632〜1704)、モンテスキュー(1689〜1755)、ルソー(1712〜78)といった思想家が、現代にもつながる政治や社会についての基礎概念をつくっていきます。また経済活動の本質をどう捉えるかということで、重商主義や重農主義の考え方が提唱され、その受容・批判からアダム・スミス(1723〜90)の経済学が芽生えてきます。国家の豊かさのための経済から、市民の豊かさのための経済への変化を象徴するのがアダム・スミスです。
自然科学の世界では、コペルニクス(1473〜1543)が「コペルニクス的転回」といわれる地動説を唱え、それをガリレオ・ガリレイ(1564〜1642)が実証し、ニュートン(1642〜1727)力学へと引き継がれます。自然をあるがままに見る自然科学の成立です。そうした諸々の実学や物理学を背景に、やがて産業革命が起きます。
中世までの大学が、文法・レトリック(修辞学)・論理学・数学・音楽・幾何学・天文学(総合して「自由七科(リベラルアーツ」)という非実用的な学問を中心として成り立っていたのに対し、新しい大学は自然科学・社会科学・人文学といった分野を擁し、とりわけ自然科学・社会科学において目覚ましい発展がありました。こうした学問の分類は、フランシス・ベーコン(1561〜1626)の分類法に拠るところが大きいと言えます。
国民国家成立の条件
西欧による新しい世界史の創設は、それまでになかった新しいものを生み出しました。それは“人間個人の豊かさ”を求めるという動きです。自由・平等・友愛といった人権概念は、宗教や国王といった、さまざまな制度から人間が独立していくなかで生まれました。時には暴力的革命、時には平和的革命によって、それらの価値が確立されていきますが、それは国民国家の形成とパラレルに起きたことです。イギリスやフランスで生まれた国民国家は、現在に至るまで我々の思考を規定しています。
まず国家という枠を決め、そこからさまざまな人権を保障していく制度は、現在どの地域でも一般的になっています。憲法という国の枠を定め、そこから派生するかたちで各法律をつくっていくことをイメージするとわかりやすいでしょう。
国家とはなにかというと、西欧ではカトリック勢力からの独立が課題でしたから、第一義的には宗教から独立した政体(統治体)ということになります。もちろんこれは、宗教間の対立をもたらします。ヨーロッパではローマ・カトリックとプロテスタントの抗争です。
国家成立の初期に見られた現象は、人民は国王の臣下(臣民)として仕えるということです。国王の子供(臣民)であるということが、国民のアイデンティティを形成します。しかし、国王が多様な国民を統治する場合は、共通言語や共通民族という近代の概念が必要になります。
主権在民という考え方は、国民国家において、初めて可能となります。改革も革命も国家単位で行なわれます。国家には経済的独立が必要なので、税の徴収、貨幣の発行権などを占有する必要があり、司法組織、軍隊や警察などの暴力組織も国家が独占します。
それまでの多くの地域では、宗教であろうと民族・言語であろうとその境界は曖昧で、国家という単位が生まれてこなければ、それらをめぐる問題は起こらなかったと言えます。もちろんそれまでも差別や偏見はあったのですが、それらは制度化されず個人的なレベルにとどまっていたわけです。
こうした国家という形態は、アジアやアフリカでは、きわめて奇異に映っただけでなく、生みの親であるヨーロッパでも当初はおかしなものと見られていました。19世紀までのヨーロッパを見渡してみて、国民国家と言えるのは、フランス、イギリス、オランダぐらいのものです。その他の地域は、大きな帝国を成すか、あるいは小さな君主国家であるかです。
しかし、19世紀以降、国民国家が世界中に“輸出”され、その動きは1918年の第一次大戦終結で決定的になりました。ヴェルサイユ条約は戦勝連合国とドイツとの講和条約ですが、他の敗戦国との講話条約によって、ドイツ帝国、オーストリア帝国、オスマン帝国が解体し、その配下にあった地域はそれぞれ国民国家への道を歩みます。
ロシア帝国は、1917年に皇帝が退位しますが、22年まで存続し、ソビエト連邦という近代国民国家の連合体に引き継がれます。アメリカも国家(州)の連合体国家(合衆国)です。すなわち2つの巨大な、社会主義の連合体国家と、資本主義の連合体国家が誕生することになったのです。
国民国家というかたちに適さない地域、あるいはそれを為すのに多くの困難な条件を抱えている地域があります。しかしヨーロッパにおいても、すんなりと国民国家に移行したわけではありません。どこも力づくでそれを実現していったというのが実態に近く、その推進役を果たしたのが憲法の制定や学校教育の普及です。
憲法(Constitution)とは「国づくり」という意味ですが、憲法の及ぶ範囲に居住する者が国民とされ、言語も統一されていきます。日本は、ちょうどこうしたヨーロッパの国民国家成立時に明治維新を興しますので、日本政府はイギリス史やドイツ史、フランス史を教科書にし、日本という国民国家をつくり上げていきました。こうした国民国家に適合しにくい(あるいは抵抗する)地域である琉球やアイヌの北海道には、厳しい同化政策が採られていきます。
近代化とは、多様な人々が必ずどこかの国家の国民にならねばならないということであり、20世紀のさまざまな不幸はここから生まれます。
産業革命と勤勉
西欧が世界史にもたらした大きなもののひとつに産業革命があります。これは18世紀半ばにイギリスから起こったもので、産業機械の発達によって生産性が飛躍的に増大しました。それ以前はアジアが世界の生産の圧倒的シェアを占めていましたが、この状況が一変します。産業革命は「Industrial Revolution」を訳したものなので、産業は工業のことだと思われがちですが、Industrial とは「最も生産的な仕事」という意味であって、たまたまそれが農業やサービス業ではなく、工業だったために、そういう思い込みが生まれました。
生産性の高さは、労働の在り方に現れますが、ここでは分業という働き方に注意を向けましょう。
分業(division of labor)とは、労働過程、あるいは生産過程の分割です。それまでも男女の役割分担や農業と工業の分立など、社会的分業はありましたが、ここで重要なのは、工場内での工程(作業)の分割、生産過程の分割です。
これは同じ仕事場にいながら、労働者によって課される仕事が違うということです。これは「工場内分業」と呼ばれますが、別の仕事をしている人間とは同志的な気持ちになりにくい。さらに、機械が仕事の中心に居座っていて、個々の労働者は取り組む仕事が結果としてなにをつくり、どんな役割を担っているのかなど、その内容を知らなくても、即日から従事できるようになりました。
そういう仕事では、労働に対する責任や研鑽の意欲が生まれにくく、ただ賃金を得ることが目的となりがちです。機械は疲れを知らず一日中動き続け、それに合わせて労働者は歯車として完全に管理・従属させられます。労働時間の延長、休日の削減によって、自ずと工場の生産力は伸びます。産業革命とは労働者が必然的に勤勉(industrious)にならざるを得ない革命、「勤勉革命」というものだったのです。
<後編へ続く>
的場昭弘(まとば あきひろ)
日本を代表するマルクス研究者、哲学者。マルクス学、社会思想史専攻。1952年、宮崎県生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士。元・神奈川大学経済学部教授(2023年定年退職)。同大で副学長、国際センター所長、図書館長などを歴任。
著書に『超訳「資本論」』全3巻(祥伝社新書)、『未来のプルードン』(亜紀書房)、『カール・マルクス入門』(作品社)、『「19世紀」でわかる世界史講義』『最強の思考法「抽象化する力」の講義』(以上、日本実業出版社)、『20歳の自分に教えたい資本論』『資本主義全史』(以上、SB新書)、『一週間de資本論』(NHK出版)、『マルクスだったらこう考える』『ネオ共産主義論』(以上、光文社新書)、『マルクスを再読する』(角川ソフィア文庫)、『いまこそ「社会主義」』(池上彰氏との共著・朝日新書)、『復権するマルクス』(佐藤優氏との共著・角川新書)、訳書にカール・マルクス『新訳共産党宣言』『新訳初期マルクス』『新訳哲学の貧困』(以上、作品社)、シャック・アタリ『世界精神マルクス』(藤原書店)など多数。